幼稚園生活
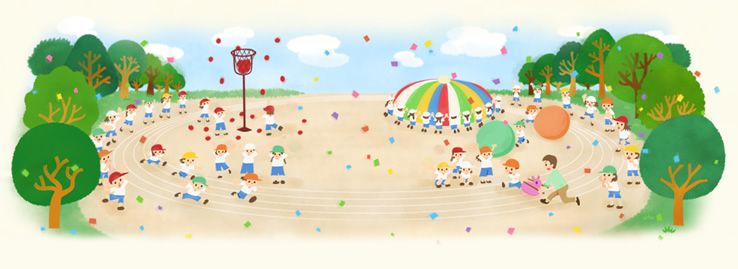
2月20日(木)に年中組が彫刻家の高橋智力先生による造形活動を行いました。今回は、はさみで切った色画用紙を白い画用紙に貼り付け、その上に絵の具で色をつけました。
それぞれ好きな色の画用紙を選んだら、自由に2本の線を決めて紙の端から端を切っていきます。「バナナみたいな形になった!」「くす玉を割ったときの形に見える!」。はさみで切った形が何に見えるか、想像が膨らんでいきます。色画用紙が切れたら、のりを使って白い画用紙に貼り付けます。「紙のどこにのりを付けたら良いか考えながら貼ってみてね。紙がペラペラしているところはないかな」。子どもたちは智力先生のアドバイスを聞いて、慎重に紙を貼り付けていました。紙を貼り付けられたら、最後にパレットに出した絵の具と筆を使って色をつけました。「筆を水でよく濡らしてから使ってね。水をつけると絵の具が伸びるよ。水と絵の具を上手く混ぜて使ってみましょう」。
じっくり考えて色画用紙の形を活かしながら色をつけた子もいれば、たくさんの色を使って色鮮やかな作品を完成させた子も。それぞれが思い思いに制作を進め、個性が光る素敵な作品が完成しました。子どもたちからは「明日もやりたい!」との声があがり、集中しながらも楽しんで取り組んだ造形活動の時間となりました。

好きな色の画用紙を選びます

さっそく色画用紙切っていきます

ギザギザに切りました

何の形に見えるかな

切った色画用紙を白い画用紙に貼り付けます

どこにのりを付けたら良いか考えながら貼っていきます

上手に貼れました!

最後に絵の具で色をつけます
水で筆をよく濡らしてからスタート

自由に色をつけていきます

色画用紙の形を活かした作品も


素敵な作品が完成しました!
ともりき先生よりひとこと
「コンポジション」
線と線に、挟み囲まれることで面が誕生します。ハサミで線を描く様に大きな画用紙を気持ちよく切ることで出現した、自分だけの面白い形。まず、ここで作り手と作品の最初の出会いがあり、この日の創作の時間が、子どもたちの笑い声や歓声に押される様に動きだします。
この自ら生み出した形ですが、実は切り出し使用する方の紙があるということは、その反対側には切り出したことで捨てる方の紙もあります。取捨選択。人生も選択の連続ですが、この「選ぶ」という決断は、時として簡単なものではないのは、大人も子どもも一緒です。考えに考えた末に「どちらか一方を選ぶなんて出来ない」と優しい涙を流したお友達も。
気を取り直して、今度は別の白い画面の上に切り出した形を置いてみます。お気に入りの形を気に入った場所に置くだけの、本当に単純な話の様でいて、実はどこに配置するかでこの後の作品のキャラクターがほぼ決定づけられる、この日の山場であり、主題でもあります。
真ん中にバランスよく配置するのか、今にも動き出しそうな迫力ある配置にするのか、それとも、雄大なランドスケープを連想させるような見せ方もできるかもしれません。「面白さ」を引き出す配置がきっとあるはずです。
特に難しい説明はあえてせずに、子どもたちの気の向くままに委ねたのですが、切る時の思い切りの良さと打って変わって、位置決めにはみんなとても慎重で、そして楽しそうにクルクルと形や画用紙を回転させながら様々な可能性を探っていました。ここがこの日一番の旨みのあるポイントだということを感覚的に理解し、それを存分に楽しんでいる時の、自信に溢れた笑顔がとても印象的でした。
最後の仕上げにはサプライズ(?)で、絵の具を使用しました。自らの作品としての構成要素をより強調したり、整えたりする為の時間となります。画面のどこの何に子どもたちが着目していたのかが、筆の動きの跡や、彩色の密度で読み取れるはずですので、今一度お家にある絵を眺めてみてください。筆が集中しているところは、きっとお気に入りのポイントなのでしょうし、色が鮮やかにいくつも重なっているところがあれば、それはきっと作品としての見せ場なのでしょう。リズムカルなドットからは、子どもたちの心がどれだけ弾み踊ったかが伝わってくるはずです。
(造形活動講師・高橋智力)