幼稚園生活
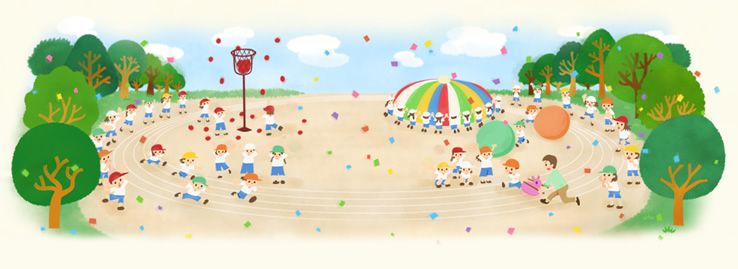
成城幼稚園園長 石井弘之
朝、幼稚園の玄関を入ると外靴から上履きに履き替えます。年少さんが入園してすぐの時期にはこれがなかなか手間のかかる作業です。そもそも自分の靴箱がどこだかわからなくなる子もいます。左右を反対に履いてしまうこともよくある出来事です。外靴が脱ぎっぱなしのこともあります。床にぺたんと座り込んでなかなか履き替えられないというのはマシな方で、何だか妙にくつろいでゴロンと仰向けになっている子もいます。「ヤダヤダヤダ」を繰り返している姿も見かけます。
私がそういう時に眺めているポイントはお母さんやお父さんの関わり方です。急いで帰らなくてはいけないのでしょう、お父さんが無理やり履かせてあげていることもあります。逆に何も言わずに見ているだけのお母さんもいます。時計を見ながら「あと2分で遅刻だよ」とせかしている方もいます。園児たちにはそのあと園長の私に「おはようございます」を、英語の教員に「good morning」を言ってから保育室に向かうという難関が控えています。
こういう時に私は、親にとっても教員にとっても「待つ」ということは至難の業であるなぁとしみじみ感じます。
中学で担任をしていたころ、新しい学期になると教室に新しい時間割表を貼りだします。私は日直か書記の生徒にA3の紙とマジックを渡して「明日までにみんなが見やすい時間割を作ってね」と依頼します。几帳面な女子なんかはその通りにやってくれますが、大雑把な男子なんかだと「あ。忘れた」ということになります。「じゃあ、明日までな」なんていうやり取りを数回繰り返してようやく時間割が貼りだされます。私はこういう「待つ」という行為が教育現場では大切なんだとずっと思ってきた古い人間です。最近は教務部がパソコンで作った時間割を拡大コピーして担任は貼るだけです。その方がずっと合理的だし楽でしょう。でも、教育現場からまた何かが失われたという老人特有の感慨が湧いてきてしまうのです。
先日、保護者の知り合いの鰻屋さんのご厚意で、鰻のつかみ取りをやらせていただきました。年少さんは樽に入った鰻を別の樽に移すというものでしたが、年長さんと年中さんはビニールプールに鰻を何匹か放して、園児もプールの中にジャブジャブ入ってつかみ取りをするというものでした。
ほとんどの園児は怖がることもなく果敢に挑戦していました。たっぷりと楽しんだ後、ヌルヌルする手を洗いに多くの園児が庭の洗面所に移動していきましたが、最後に年長の男の子と女の子ひとりずつがプールに残ってつかみ取りを続けていました。二人きりになってからけっこうな時間が経っています。プールサイドには担任のH先生。ちょっと離れて私。手を洗い終わった園児たちは保育室にどんどん戻っていきます。H先生は二人と会話はしていますが、全くせかすことをしません。二人が満足して自らプールから出るまで見守り続けていました。正直に言うと私は「さあ、そろそろ終わりにしようか」と声をかける衝動に襲われていたのです。たぶんH先生がそこにいなかったら、そうしていたと思います。
実はその日は、この出来事をさほど意識はしていませんでした。後日、来年度の受験を希望されている方との園長面談の時に、その話をしているうちに、じんわりと「スゴイなぁ。オレはまだまだだなぁ」と思い知ったのでした。
「待つ力」。次に予定があったり時間枠が決まったりしている場合は別ですが、そうじゃない時には、トコトン飽きるまでやりたいことをやらせる。幼稚園は、いや人を育てるというのは、そこが肝心なんだと改めて感じさせられる出来事でした。