幼稚園生活
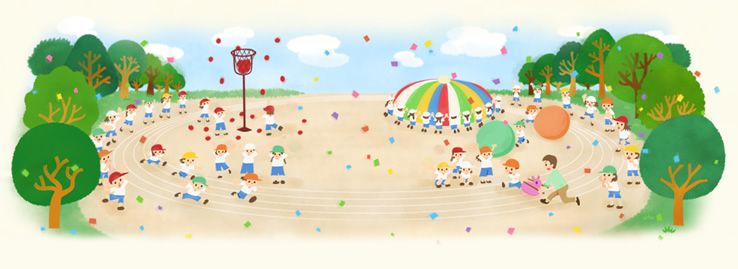
2025.09.24
皆さんはご自身のお子さんにどのような人になって欲しいと願っていますか?
「友達に恵まれた人生を送って欲しい」、「好きなこと・得意なことを見つけて夢中になって欲しい」、「スポーツを頑張ってもらいたい」、「勉強もできたら嬉しい」。考え出せばきりがなく、親の子どもに対する思いは本当に深い。言い換えれば親の愛情でもあるのだと思います。そのような中でも、「周りの人に優しくできる人に育って欲しい」と思っている方は、大勢いることと思います。
子どもたちの中にどのように優しさの芽が育まれていくのでしょうか?先日ある出来事を通して改めて考えさせられましたのでご紹介したいと思います。
幼稚園の2学期が始まって2週目の出来事です。年少組の子どもたちは、園庭で夏休みの間に脱皮したセミの脱け殻探しに夢中になり、毎日驚くほど多くの脱け殻を見つけては持ち帰っていたのですが、徐々に見つからなくなり、下火になってきていました。毎日園庭で見つけたものを持って帰り、「おみやげ~!」とお家の方に渡すのを楽しみにしていた子どもたちは、「次は何を探そうか?」と色々な場所に探検に出掛けていました。すると、クラスの何人かの子が「あっちにどんぐりがあった!」と報告をしに来てくれたので、「どんぐり探検隊」と称し、ペットボトルで作った個人持ちのバッグを手にさげ、みんなで出掛けることにしました。ちょうど、幼稚園と初等学校の校庭がフェンス越しに繋がっている場所に、どんぐりの木があり、毎年沢山のどんぐりや、どんぐりの帽子の部分が落ちてきます。子どもたちは2~3日の間、夢中になってどんぐり探しをしました。しかし、そこのどんぐりも徐々に目を凝らさないと見つからないようになり、「なかなか見つからない…先生、一緒に探して!」ということになってきました。「どこに落ちているかな…」と私も一緒に探していると、一人が、「あっちに沢山落ちている!!!」と初等学校のグラウンドを指差しました。確かに金網のドア1枚隔てた隣の初等学校のグラウンドには、まだ手付かずのどんぐりが、びっしりと落ちていました。どんぐり探検隊の子どもたちは、とっておきの宝物を見つけたかのように目を輝かせて、みんな口々に「あれが欲しい!!」と叫びました。
初等学校では授業もあるし、勝手に敷地に入るのも如何なものか…と私は悩んでいたのですが、あまりにも子どもたちがワイワイやっていることに気がついた初等学校の男の子が2人、「どうしたの?」と声をかけてくれたのです。誰だろうと思い顔を見てみると、なんと4年前に幼稚園を卒園した、昔担任をした学年のA君とB君でした。
A君:「先生、久しぶり!この子たち何歳なの?かわいいね。」
B君:「みんなどんぐりが欲しいのかな?」
と言うと、2人は初等学校のグラウンド側にあったどんぐりを素早く集め、幼稚園側に手で押し流し始めました。
年少組の子どもたちは「待ってました!」と言わんがばかりに、すぐさましゃがみこんで押し流してもらったどんぐりを拾い始めました。
私が子どもたちに「よかったね!うれしいね!」と言うと、子どもたちの口から自然に「ありがとう!」という感謝の言葉が溢れました。A君もB君も嬉しそうです。
様子を見ていた周りの子が、どんどん拾いに来るので、A君とB君は手で集めていては間に合わないと思ったのか、次に私が見たときには、グラウンドを平らにならす為のトンボをどこからか持ってきて、一度により多くのどんぐりを集められるようにしてくれていました。
汗をかきながら一生懸命、幼稚園の後輩たちのために行動してくれたA君とB君。幼稚園を卒園した子どもたちが、相手のことを考えながら自ら進んで行動できる人に成長していることが本当に嬉しく、涙が出そうになるほど感動しました。
最終的に、1日の遊びの時間では拾いきれないくらいのどんぐりを集めてくれたA君とB君。お別れの時間になり子どもたちと一緒に改めてお礼を言いました。幼稚園の子どもたちに「おにいさん、ありがとう!」と言われたA君とB君は少し照れて、「今度君たちより年下の子が入ってきたら優しくしてあげるんだぞ」と言いました。
その言葉に力強く頷く年少組の子どもたち。きっと「人に優しくする」ということがどういうことなのかを、肌で感じ、理解したのではないでしょうか?そして優しさは自分が受けとるだけではなく、自分にとって大切な誰かのために返していくものだということも感じたはずです。
成城幼稚園では、ホールで全学年が集まりをする時に年長組が年少組の分の椅子を用意したり片付けてくれたりすることもあります。文化祭の共同製作では、経験のある年長組が初めて製作に参加する年中組をサポートし、リードします。
『自分がしてもらって嬉しかったことを、次は誰かにしてあげたい』。そのような思いが目には見えない伝統として残る幼稚園だと思います。
「人に優しく」と言葉で言うことは簡単ですが、本当の意味を理解するためにはまず自分が優しくしてもらって嬉しかったという経験が必要です。
日々の保育の中で子どもたちのこのような温かなやり取りの瞬間を目の当たりにし、共有できるのは教師として本当に嬉しいことであり、私にとっての幸せでもあります。
周りの愛情や優しさを沢山感じながら育った今の年少組の子どもたちも、いつかそのような存在へ成長していくことを願っています。









